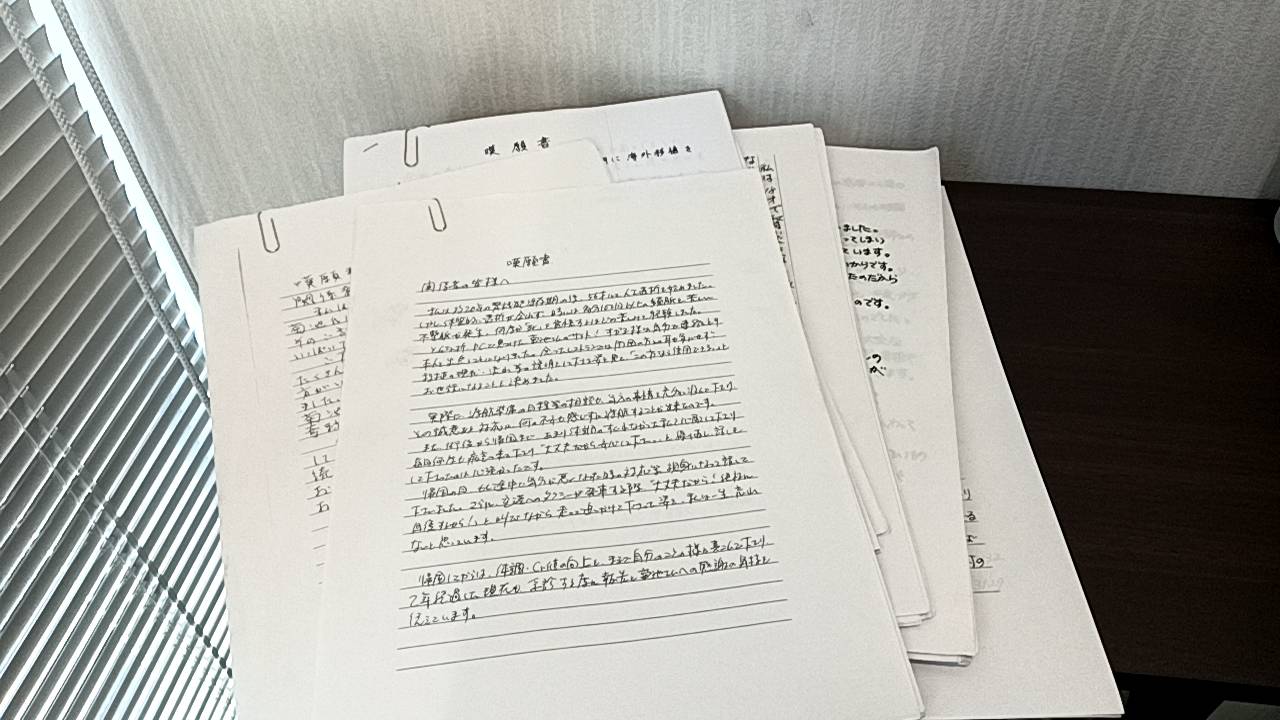海外臓器移植支援の真実と現在の裁判について
事件の経緯と現在
はじめに
日本では毎年1万名を超える臓器移植待機者が、適切なドナーと巡り合うことなく命を落としています。こうした現実を前に、私は2007年より、海外の公的な医療機関と連携し、非営利にて海外渡航臓器移植支援を行ってきました。
高額と言われる海外移植治療費を通常の半分以下にて成し遂げています。詳細は本文のエビデンスをご確認ください。
この活動の中で、私は170名(※注1)以上のレシピエントと向き合い、そのうち約110名(約4割は肝臓移植)の方々が渡航し約100名が移植治療によって命を救われ、社会復帰(※注2)されています。
しかし現在、私は「臓器移植法第12条違反」を根拠とした刑事事件の被告人として裁判の渦中にあります。ここでは、この事件の経緯と現在の争点について、また報道では語られていない事実関係を詳しくご説明いたします。
(※注1)2019年までは海外医療機関の受け入れ審査が厳しく、約3割の方が渡航を希望しても不許可となっていました。特に60歳以上は原則、受け入れ不可でした。貴重なドナーは若い人を優先する判断からです。
(※注2)マスコミ各社は移植後の経過が思わしくなかった一部の患者事例のみを取り上げ、あたかもそれが全体像であるかのように報道しました。しかし、これは実態とは異なります。
12条違反とは「厚生労働大臣に認可を受けずに、海外渡航の支援活動を「業として行った」罪です。
しかし、私は率直に申して厚生労働大臣の許可を得なければ人の命を救うことさえ許されないのか、大きな疑問を抱いています。(現在、最高裁判所にて係争中)
1. 刑事事件に至るまでの経緯
| 条文番号 | 条文の趣旨 | 違反の定義 | 本件における関係性・指摘 | 本件における状況 |
| 第11条 | 臓器の売買禁止 | 臓器の提供またはあっせんに関して、金銭その他の利益を受け取ることを禁止(営利目的の禁止) | 「高額費用を要求」「暴利」との報道によって11条違反の疑念が流布された | ✅警察による捜査の結果、営利性は否定され、逮捕・起訴もされていない ✅東京地裁も「営利目的性は認められない」と判断 |
| 第12条 | 臓器のあっせん行為には厚労大臣の認可が必要 | 臓器の提供者と移植実施施設との間を業としてあっせんする場合、厚生労働大臣の認可が必要 | 厚労省の解釈により「海外医療機関への紹介等も該当し得る」とされ、無認可支援が違反とされた | ✅ 「提供施設↔移植施設」ではなく「患者↔海外病院」支援のため、当初は適用対象外と認識 ✅ 2022年に厚労省より初めて解釈通知あり |
2.東京地裁による「営利目的の否定」 (刑事事件と民事事件)
a) 支援の出発点は日本大使館からの紹介
2006年、患者側の要請を受け、在ベラルーシ日本大使館に照会を行いました。大使館は、ミンスク市内の国立移植医療センターを紹介し、元大使館員セルゲイ氏を医療交渉の窓口として推薦しました。
b) 交渉と契約は正式ルートで
この推薦を受け、私はセルゲイ氏と共に現地病院との交渉を進め、渡航・受入・費用・術後管理などの細則を明文化し、正式契約に基づいた移植支援を構築しました。
c) 支援費用は「○○ちゃんを救う会」の半額以下
例:肝移植例で約2,800万円+予備費、同医療機関で別団体が扱った金額(7,500万円)と比較し、半額以下での移植支援を実現しています。
d) 余剰金の返金と家族からの感謝
患者側に返金された金額は300万円にのぼり、その実績は証拠文書と感謝メール等で立証されています。
2-1.営利目的の否定
2023年、東京地方裁判所は、臓器移植法違反の刑事事件において、私および当会に対して「営利目的は認められない」との明確な判断を示しました。
判決では、当会が医療紹介料や中間マージンを一切受け取っていないこと、および活動全体が非営利の趣旨に基づいていることが正式に認定されています。
しかしその一方で、NHK・読売新聞・週刊文春などの大手報道機関は、これと同時期に「臓器売買」「暴利を貪る支援団体」などの扇情的な表現を用い、社会的反響を狙った一方的な報道を繰り返しました。
これらの報道の大半は、裏付け取材や反証の機会を当会に与えることなく、一方的な供述情報をベースとして構成されており、報道倫理の根幹である「中立性」や「バランス感覚」に明らかに欠けるものでした。
2-2.背後にある、情報源の偏りと意図的な印象操作
こうした報道が成立する背景には、以下の3者による主導的な情報提供があったことが判明しています。
元職員2名:退職時に「5,000万円を退職金として支払え」と要求し、これを拒否されたのち、当会の内部録音(計16時間を部分的に切り取り)をマスコミへ提供。「臓器売買の証拠」として歪曲した内容を売り込んだとされています。
✅元職員による新聞配布と退職金の要求(jpg)
一部のレシピエント:支援を受けた立場でありながら、当会の批判者として元職員と結託して、マスコミ取材に応じ、「パスポート偽造」「移植後の医療トラブル」などを、あたかも当会が関与し、責任があるかのように訴え、報道の材料となった。
取材記者自身の先入観:臓器移植=グレー、仲介=違法、という先入観から、当会に対して初めから批判的姿勢で取材を進め、当会側の見解や証拠資料は一切参照せず、一方的な加害者像としてストーリーを構築したケースが散見されました。
結果的に、これらの偏った報道により、活動の本質や支援実績を一切無視したイメージが拡散され、多くの移植希望者が支援をためらう事態に陥りました。
2-3.名誉回復と訂正報道を求めた民事訴訟
こうした事態を重く受け止めた私は、報道によって名誉と信用を著しく毀損されたとして、NHK・読売新聞社・週刊文春(文藝春秋)を相手取り、計2億2,000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。
当訴訟においては、刑事判決における「非営利性の認定」や、「返金実績の存在」「患者からの感謝証言」「報道前に反論機会を与えなかった事実」など、客観的事実と一次証拠に基づく反論を全面展開しています。
このように、刑事事件の判決内容と、メディアが流布した印象との間には大きな乖離があります。
そしてその背景には、個人的利害関係者による策略と、それを一切検証せずに報じた報道機関の責任が明確に存在しています。
この点を理解していただくことが、当会の活動の正当性を見直し、今後、移植を希望する方々が委縮せずに相談できる環境づくりの第一歩になると信じております。
3.上告審(刑事事件)における争点と私の立場
東京地裁は「紹介料なし」「営利性なし」を明確に認定しました。
上告は実質的争点というよりも、形式的確認にとどまる審理であり、裁判の本質とは関係の薄い内容です。それでも私は、将来のレシピエント支援を円滑に進めるため、正式な無罪確定を目指すという信念で争っています。
4.元職員による「乗っ取り工作」の発端
本件の最大の転機は、元職員2名が退職金名目で5,000万円を要求し、それが私に拒否された後、16時間に及ぶ隠し録音を「臓器売買の証拠」としてマスコミ各社へ拡散したことでした。
この録音には違法性を示す内容は一切含まれておらず、警察の捜査でも、私への聞き込み捜査を経て立証に至らないままです。しかしながら、この悪質な情報操作が、社会的批判と誤解を生み、現在の状況へと繋がっています。
✅【・・様メール】感謝のやりとり(png)
5.これまでに救えた命は約100名
17 年間で当会が支援した170名のうち、約60名は「渡航前検査」にて移植不適応と判断され、渡航の断念、あるいは現地に渡航したものの、手術を受けずに帰国されました。
また、約10名は術後合併症や感染症などにより、現地または帰国後間もなく、不幸にも、お亡くなりになりました。しかしながら、この死亡率は国内で移植術を受けた場合と比較しても有意な差はございません。
結果として、約100名が健康を取り戻し、現在も社会生活を送っています。しかし、これらの成果は報道では一切触れられていません。
✅B様費用内訳、感謝メールなど(docx・png)
6.臓器移植法12条「海外あっせん」の適用外論
私の活動は、日本国内の「臓器提供施設↔移植実施施設」を対象とした臓器移植法第12条の規制外にあると考えています。
・立法当初から12条は 国内施設間を想定
・当会は 日本人患者と海外公的医療機関との橋渡しのみ
・厚労省の逐条解説に「海外」が明記されたのは法改正後の補足であり、条文自体には変更なし
・過去16年間、厚労省・警察のいずれからも、私たちの活動に違法性の指摘はありませんでした
7.非営利での徹底した運営
職員は エコノミークラス航空券を原則とし、宿泊は3星以下の施設を利用していました。
私の年収は 17年間で 350〜450万円に抑え、贅沢な支出は一切していません。
このように活動全体を通して、極力経費を抑える運営に努めておりました。
また、必要経費を除き、余剰は全て患者に返還しております。
この点については、関係機関による厳正なる捜査の結果、私的流用はなく、営利目的のあっせんや金銭の私的流用といった違法行為の事実は確認されず、結果として、臓器移植法11条(営利あっせん)逮捕も起訴もされていません。
8.帰国後の医療フォローと国内医師の応召義務
臓器移植後の患者は、生涯にわたり、免疫抑制剤の内服と定期的な通院が必須となります。
しかし、現実には帰国後に診療拒否を受けるケースが数多く発生しています。これは応召義務を定めた医師法第19条の趣旨に明確に反しており、人道に基づく医療の放棄とも言える重大な社会課題です。
「イスタンブール宣言」を拡大解釈し、海外移植者を単に「臓器売買者」として誤認する風潮が一部の医療機関に蔓延しているためです。
私はその都度、国会議員や自治体の議員とも連携し、受診可能な医療機関との橋渡しを行ってきました。実際にあるレシピエントが帰国後に受診拒否された際は、国会議員を通じて医療機関側と折衝し、受け入れ体制を整備しましたが、最近は市民の代表である議員の申し入れも拒否するケースが増えて参りました。
診療拒否の不法行為を繰り返す医療機関に対し監督官庁である各地域の保健所は厳格な対応で臨んで頂きたく思います。
私の活動は「帰国後も責任を持って寄り添う」という姿勢のもと、支援は「移植成功で終わり」ではなく、その後の人生にも関与し続けることを信条としています。
9.国際比較から見える制度の歪みと日本の課題
世界には、臓器移植を公費で全額支援する国が複数存在します。
例えば、
▼イスラエル
死体ドナーが原則禁止である宗教的背景をふまえ、国費で渡航・手術・宿泊・家族の同伴費用まですべて補助。
▼イラン
シーア派社会における制度化された生体間移植支援。
▼CIS諸国
公的医療機関による臓器配分制度と外国人(CIS諸国に限る)受け入れ実績が整備されている。
一方、日本では、国は「死体ドナーを受け入れる法制度」を整備しておきながら、現場では提供が進まず、年間数千名が移植待機中に死亡するという矛盾が長い間放置されてしまっています。
宗教的には許されているにもかかわらず、社会的・情緒的な理由(「死体に手を加えるのは不謹慎」など)から、臓器提供が進まないのが正直な現状です。
これこそが「なぜ日本人が海外で移植を受けざるを得ないのか?」という本質的課題であり、それを民間団体がカバーせざるを得なかった背景でもあります。
10.臓器移植法第12条と「海外案内」への誤適用
臓器移植法12条は、当初より「国内の提供施設と移植施設の間での“業としてのあっせん”」を規制するものでした。
ところが2010年頃に「逐条解説」に、「海外医療機関への受診を容易にする行為も含まれる」とする文言が追加され、事実上の「行政の裁量解釈」による規制拡大が始まりました。
この文言追加に関しては、当時の政治関係者や業界関係者の間でも「日本透析学会」や「日本移植学会」の意向が背景にあるとの認識が広まっていました。
・国内移植が進まず、透析医療が長期ビジネス化している実情
・民間支援による回復者が出ると困る業界構造
・国が海外移植を認めたくない、という政治的空気
こうした事情が、規制の拡大解釈という形で臓器移植法12条に反映されたと見られています。
この点については、厚生労働省自身も解釈を明言できず、私がヒアリングを要請しても回答が二転三転するという事態が記録として残っています。
11.過去の捜査協力と、違法性の否定
私はこれまでに少なくとも3件の海外臓器売買に関する警察捜査に協力してきました。
兵庫県警、愛媛県警、警視庁生活安全課
いずれのケースでも、最終的に逮捕・立件に至ることはありませんでした。
また、これらの捜査の過程で、警察から「臓器移植法12条に違反する」との指摘を受けたことは一度もありません。
なぜなら、私は「臓器提供施設と移植施設の間に立って臓器を配分する」という活動は一切しておらず、あくまで日本人レシピエントが現地の医療機関にアクセスするための「受診支援」のみを行ってきたからです。
つまり、現地の臓器の出所や配分には一切関与していないというのが活動の実態であり、まさに12条の「想定範囲外」であるという点に尽きます。
12.医師の診断に基づく支援と「○○ちゃんを救う会」との違いのなさ
私が移植支援に関与する際、主治医の診断がなければ一切の手続きは進めていません。
常に「臓器移植が最良の治療」とする医師の意見書をベースとし、その診療情報提供書を翻訳し、現地医師に渡すという手順を踏んでいます。
これは、「○○ちゃんを救う会」がやっている流れと何ら変わりません。患者の希望、主治医の判断。情報提供・翻訳・渡航支援です。
いずれも、医師の診断に基づいて、民間がサポートする形式であり、私や当会のみを「臓器ブローカー」などと断じるのは明らかに不当で残念なことです。
実際、当会では報酬目的の仲介、リベートの授受などは一切なく、すべての契約・領収・返金の記録を証拠として保持していますし、警察への捜査でもすべて開示したところ、営利目的なしと判断されています。
13.本件起訴と個別レシピエント事案の実態
今回の刑事事件の起訴内容は、ベラルーシでの腎移植を受けたAさんおよび肝臓移植を受けたBさんに関わるものでした。
13-1. 大使館を通じた正式な病院紹介
AさんおよびBさんの案件はいずれも、在ベラルーシ日本大使館への照会に基づいて始まっています。領事館より、臓器移植の実績ある公的医療機関が紹介され、さらに通訳として元大使館員のセルゲイ氏が推挙されました。
13-2. 招聘状の発行と医療手続きの合法性
ベラルーシ政府より正式な招聘状を発行された上で、両名は合法的な医療手続きを経て渡航・治療を受けています。
Bさんは手術直後の容体は安定していたものの、帰国半年後に感染症を発症し、移植肝の機能が廃絶しました。しかしこれは肝移植患者における統計的リスク(15%前後)と一致する自然経過であり、医療行為そのものの瑕疵や、支援活動の不備によるものではありませんでした。
加えて、私ども支援団体は、医療機関ではなく、医療の実施や結果について直接責任を負う立場ではないことが明らかです。
それにもかかわらず、個別の医療経過を支援団体の責任と結びつけるかのような論調で、一連の報道は事実関係を冷静に分析・検証することなく、感情の赴くまま、かつ、一方的な印象を与える報道がなされたことは極めて遺憾です。
13-3. 医師の診断書・患者の同意・適正な金銭授受
・主治医からの診断書と診療情報提供書に基づいて支援が開始
・会からのサポート内容、費用、リスクをすべて説明
・契約書・領収書・返金記録すべて文書で保存・提出済
つまり、違法性はどこにも存在しないにもかかわらず、事後的に構成された法的論理により、本件は起訴に至っていると私は考えています。
14.海外医療機関との実際の連携と信頼関係
私は海外の国立病院や大学病院と、10年以上にわたって公式な関係を築いてきました。
14-1. 中国・ベラルーシとの制度的な関係構築
・中国・天津
移植医療に特化した国家的医療センターと連携
・ベラルーシ
在外公館の関与を経て、国立病院より正式に受け入れ認可を取得
これらの病院では、ドナーの選定・移植可否の判断は医師および当該国政府あるいは地方行政の責任下で行われており、私や支援団体が介入する余地は一切ありません。
14-2. 学術交流と医療の透明性向上
・2009年、東京女子医科大学にて中国の臓器移植チームとの公開学術交流を開催
・故加藤紘一衆議院議員の尽力により、日本移植学会理事長(寺岡慧教授)を招聘し、講師として登壇
・中国・中南大学 湘雅三院の医師3名(全員が国費留学の博士号取得者)を迎えた
このように、学術・医療両面での公開的な活動を行っており、秘密裏に違法行為が行われていたという主張は完全に虚偽です。
-2-1024x768.jpg)
15.今後への提案と願い~制度の空白を埋めるために
私が直面しているのは制度の欠落によって生じる「命のグレーゾーン」です。
これを放置したまま、民間の努力だけを犯罪視するような社会はあまりに非人道的ではないでしょうか。
15-1. 制度不備の3つの問題点
➢臓器移植法12条の解釈拡張と適用外不明確
海外移植への支援が「業としてのあっせん」に該当するか否かが、未だ明確に整理されていない。
➢国民の移植選択の自由と海外封鎖政策
自費渡航にまで規制を設けようとする動きは、憲法が保障する自己決定権と衝突する。
➢厚労省による事後的見解の押し付け
法文に明記がないにもかかわらず、「逐条解説」やヒアリングで初めて、支援も違法と言われる構造。
15-2. 制度設計の是正と患者本位のルール整備
➢日本国内の臓器移植数とドナー提供率を正面から見直すこと
➢海外渡航希望者への正規ルートと認可制度の創設
➢民間支援団体が違法視されず、透明性をもって活動できる環境整備
これらを国会で真剣に議論する時期がきています。
15-3. 私の願い
私は制度の欠落と誤報道によって、命を救えたはずの患者が支援を受けられなくなることを何よりも恐れています。
「命を救う行為を犯罪として扱う社会であってはならない。」
その想いを胸に、私は本件裁判を通して、すべての誤解と不正義に向き合ってまいります。
結びに
「命を救いたい」という一心で、私は今日まで活動を続けてきました。
国内で臓器提供を満足に受けられないという現実がある限り、患者に最良の道を示すことが人道であり、正義であると信じています。
そして今、歪められた報道や偏見によって、未来あるレシピエントが支援を諦めることのないように、正しい事実の開示と説明責任の履行を、私はこれからも続けてまいります。
※本ページは医療行為の勧誘を目的としたものではありません。治療の最終判断は関係医師とのご相談のうえ、ご自身の責任にて、お願いいたします。